クッカリーサイエンス
『クッカリーサイエンス』の紹介
日本調理科学会監修の『クッカリーサイエンス』シリーズです。建帛社より出版されています。
001 加熱上手はお料理上手—なぜ? に答える科学の目—
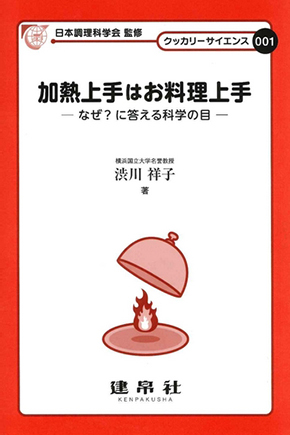
渋川 祥子 著 2009年6月20日 発行
調理における加熱の研究に長年関わってきた著者が熱の伝わり方の基礎から加熱機器の原理、使い方までを広く説明し、加熱を上手にコントロールすることの大切さを伝えるとともに、加熱に関する調理のなぜも展開され、加熱がぐっと身近に感じられてくる。
特に焼く操作に関してオーブンにおける放射伝熱と対流伝熱の割合、スチームコンベクションオーブンにおける過熱水蒸気、遠赤外線加熱、炭火焼き、など興味深く役に立つ情報が豊富である。
002 だしの秘密—みえてきた日本人の嗜好の原点—
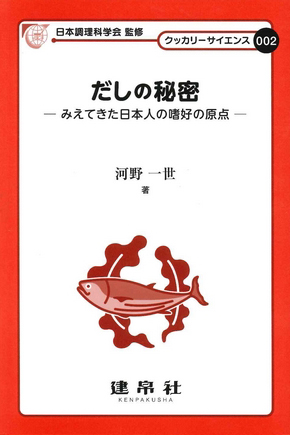
河野 一世 著 2009年9月25日 発行
昆布とカツオ節からとる日本のだしを中心に日本人がどのようにだしと関わってきたのかについて歴史資料をひもとき、さらに他国でのフィールド調査から地域間での共通点や相違点を比較している。
その裏付けとなる成分分析やだしの官能評価を行い、調理科学的知見を加えるとともに、だしは嗜好性が高いだけでなく"体によかった"から人類が食べ続けてきたのだ、という歴史的事実を踏まえて、だしの健康機能についても紹介している。
003 野菜をミクロの眼で見る
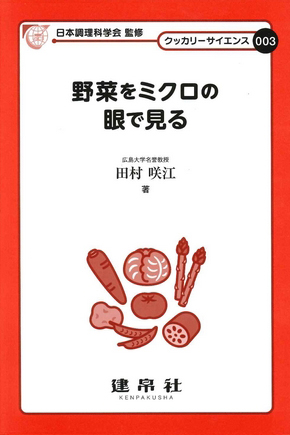
田村 咲江 著 2012年5月10日 発行
本書は野菜と若干の果物、いも、豆を取り上げて食品のミクロの構造とその生体としての働きを解説し、さらに含有成分の分布の調べ方、加熱や冷凍などの調理操作の影響などを光学顕微鏡と透過型および走査型電子顕微鏡の写真を用いて詳しく述べている。
特に透過型電子顕微鏡による細胞壁周辺の画像は倍率数千倍以上で鮮明で圧巻であり、加熱前後の試料を観察し、また同一試料を光学顕微鏡と比較したことでサイズ感を実感しやすくしている。
004 お米とごはんの科学
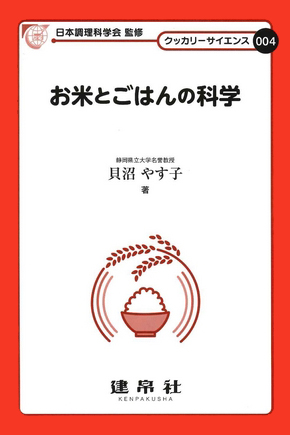
貝沼 やす子 著 2012年8月25日 発行
本書は米の調理をテーマに約40年間研究を進めてきた著者が、米料理に対する時代の要求を意識しつつ、最終的には日常の食生活に役立つ成果を目指した研究をまとめたもので、炊飯に関する基本的な事項とともに多様な米の調理の可能性を示唆する研究事例も紹介している。
おいしいごはんを炊くコツ、緑茶や柑橘果汁を添加した炊飯、米調理への竹炭利用、米ペーストのパンへの利用など、米は古くて新しい魅力的な食材である。
005 和菓子の魅力—素材特性とおいしさ—
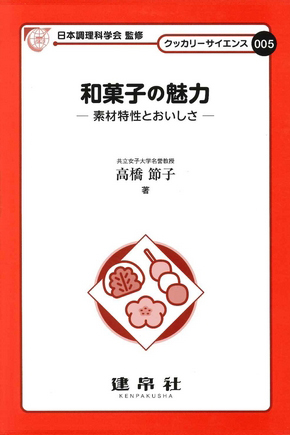
高橋 節子 著 2012年12月10日 発行
和菓子は日本の様々な年中行事と一体になって現代まで伝えられている。伝統食品としての和菓子は種類が多く、多様な原料、幅広い手法など奥が深い。
本書では、和菓子をつくる楽しさ、食べるときの喜びをいっそう深めるために、まず和菓子の歴史をたどり、基本的な和菓子の作り方と要点、さらに家庭でできる和菓子の簡単レシピを紹介している。
菓子小史や年中行事と和菓子の関係をまとめた一覧は和菓子を概観し、見て楽しむ一助となろう。
006 科学でひらくゴマの世界

福田 靖子 著 2013年2月20日 発行
ゴマは農耕文化発祥時からの作物であり、6000年以上のゴマの歴史とその食文化は人類の歴史とも重なるほどである。
研究の歴史は浅いが、伝承に過ぎなかったゴマの抗老化作用について抗酸化という視点からの研究によってゴマリグナン類の存在や健康機能が実証されている。
ゴマリグナンを研究する著者は、健康増進機能や調理加工、食文化の視点からゴマの魅力に迫り、ゴマが古来人々に可愛がられ続けている秘密&謎を解こうとしている。
007 油のマジック—おいしさを引き出す油の力—
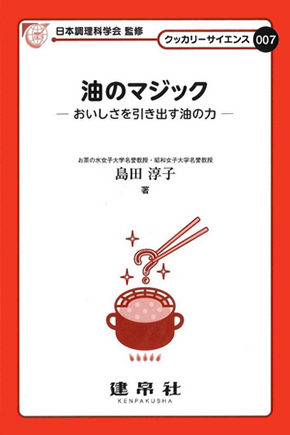
島田 淳子 著 2016年8月5日 発行
油そのものには味はないが、野菜など天ぷらや炒め物にするとおいしくなる。なぜだろうか? 本書の趣旨は、このような「油と調理とおいしさとの関係」を科学の目で見つめてみることにある。
調理に関わる油の性質や役割、関連する感覚用語などとともに、例えば重いといわれるゴマ油のその理由について、ゴマ油の重い感じが特徴ある匂いによるのではなく、圧搾による微量の不純物に由来するという自身の研究結果を紹介している。
008 泡をくうお話—ふわふわ、サクサク、もちもちの食べ物—
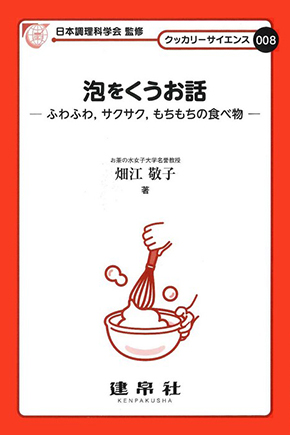
畑江 敬子 著 2017年5月10日 発行
スポンジケーキやまんじゅうなどのデザートは、小麦粉や米粉に副材料を加えて加熱し、ふわふわした口触りをもたせている。いずれも調理過程で抱き込まれた泡の空気が加熱時に膨張し、空洞として残った構造によっている。
その泡の程度と物性の関係を和洋中のそれぞれのデザートの例を挙げて写真付きで説明している。例としてアイスクリームをスポンジ生地で包みメレンゲで覆って焼いたベイクドアラスカ。その鍵はメレンゲ層の断熱性に。
009 食を支えるキッチングッズ—調理用具,電気・ガス機器とつき合う—
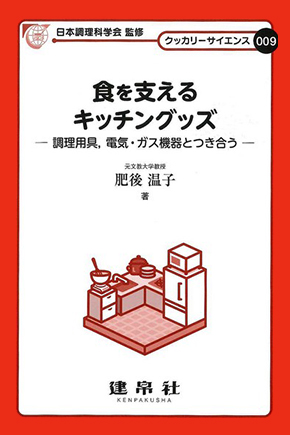
肥後 温子 著 2018年8月1日 発行
本書には「食べ方」が多様化した昨今、家庭内の調理を支えてきた「調理用具・調理機器」の存在を再認識して欲しいという思いが詰っている。
日本の一般家庭に存在する調理用具・調理機器は100種類以上あるが、かつて「台所道具」とよばれた調理用具がなぜ「調理機器」となってきたのか。
著者が調理機器を操作別、仕様別に分類した一覧を眺めると、調理機能を多目的にした複合型や熱源内蔵型の加熱器が家庭用に製造されてきたことが伺える。
010 ふくらむ加熱調理—コロッケのはれつ・ドーナツのきれつ—
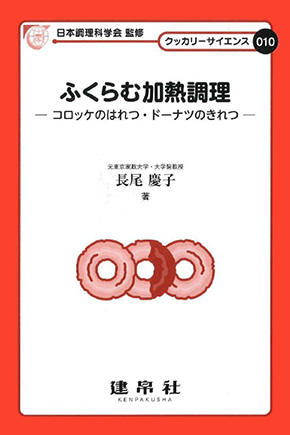
長尾 慶子 著 2022年8月30日 発行
コロッケを揚げる時に起こるひび割れは見た目が悪く好まれないが、ドーナツではむしろ好まれるときもある。
本書はこのような調理中に起こるひび割れ(本書ではきれつと総称)の発生メカニズムを考察し、一般式化し、それを実際の調理の中で実証し、さらに改善法も提案している。
加熱時に内容物が膨張する際に押す力の内部圧が発生し、それを外皮の強度で抑え込む(きれつ圧)が、内部圧がきれつ圧を上回るときれつが発生する。
011 米粉調理で広がる世界
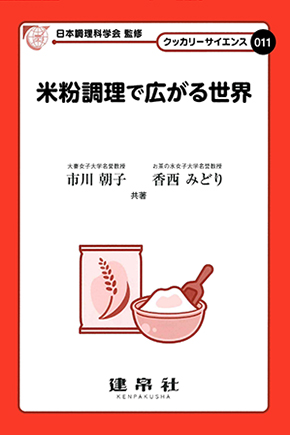
市川 朝子・香西 みどり 共著 2023年9月15日 発行
現在、米粉といえば、近年の粉砕技術の著しい進展によって小麦粉にかなり近い状態になった微細な米粉を指し、従来の米粉は食品成分表では「上新粉」や「白玉粉」と記載されている。
本書は日本人の貴重な食材である米の利用として米粉に着目し、調理の幅が広がり食生活が豊かになると共に日本の食料事情の向上を図ることを目指している。
小麦粉との比較や項目ごとにもうけた「まとめ」、写真付きの米粉調理例など活用しやすくなっている。
012 おいしいたまごのはなし
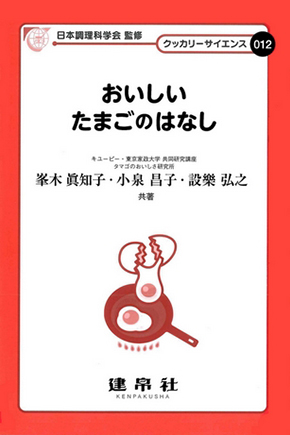
峯木 眞知子・小泉 昌子・設樂 弘之 共著 2024年4月15日 発行
たまごといえば鶏卵であり、栄養価が高く消費量も多い身近な食材である。
本書はおいしいたまごを産む鶏の条件やスーパーに並ぶまでの話、たまごの品質、栄養成分、料理をおいしくするたまごの働き、卵料理のおいしさ、などをまとめており、14の料理QRコードから作り方の動画をみることができる。
鶏の話や卵の組織構造、調理した卵の顕微鏡画像などたまごに関わる広範な知識や情報が提供され、たまごの魅力を改めて知ることができる。
